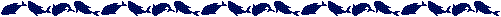
「駒ヶ根市・中心市街地の活性化について」
2003年10月20日
小 原 茂 幸
かつて子供の頃(昭和30年代)には「町へ行く」と親に言われたときには、
ウキウキしたものがありました。
広小路や銀座通りは駒ヶ根市の中心として人が溢れる賑やかな通りでした。
路線バスや国鉄が全盛の時代のことです。
やがてモータリゼーションの発展によって、マイカー時代が到来し、平行して公共交通が廃れ、
これが更にマイカー時代を推し進め、結果として、駐車場のある郊外の大型店へと商業地が移動していきました。
今や中心市街地には空店舗や空家が目立ち、かつての活気はごくわずかしか残っておりません。
古来より「町」は「物と人と情報」が行き交う場所でした。
町は本来「市場(楽市楽座)」であり、そこには夢があったはずです。
そこで、3つのまち作りを提案します。
①「環境都市」21世紀は環境の時代だといわれています。
町の中に「花とみどりと水」を整備し、潤いのあるまち作りを行います。
人口爆発、食糧難、地球温暖化など、地球規模で考えて地域で行動する時代です。
「食とエネルギーの確保とゴミ問題」。
地域自給、地産池消の循環型社会として、郊外の農産地と連携し、
「日本一の環境都市・駒ヶ根」を目指すべく、情報を発信し、連携を深め、美しいまち作りを進めます。
「美しさには人を惹きつける力があります」。
二つのアルプスが見える美しい景観の美しい街を創造しましょう。
②「福祉のまち」日本が迎えようとしている少子高齢化社会。
これを背景にまちを考えたとき、
中心市街地の中に、「デイサービスセンター」と「保育園」、「学童預かり」を集合させる事を提案します。
空店舗や空家を活用して「様々な形態のデイサービスセンター」を開設し、ネットワークさせます。
10人規模のデイサービスセンターが10軒集まれば100人の規模になり、
保育園ともども、毎日送迎がなされ、必然的に町に行く機会が増えます。
高齢者と幼児を隣り合わせにする事で、世代間の「育み」が発生します。
高齢者や幼児に安全なバリアフリーの町を目指し、ボランティア活動などの人材の確保も容易になります。
なじみの店舗に昔からの客が復帰します。福祉のまち作りで地元の人々を呼び戻します。
③「手仕事屋のまち」人間の健康は「手」と「足」をいかに使うかが大きく作用しています。
現代人の病気の根源といわれるストレスも、かつては、編物、パッチワーク、縄ない等の手仕事でかなり解消できたとの事です。
滋賀県長浜市の黒壁は「ガラス」でした。
駒ヶ根は、民が始めた「くらふてぃあ」の工芸と、
青年海外協力隊の活動地である発展途上国の民芸品などを展示する、「手仕事」を中心にしてみたいと考えます。
たとえば、北町の駐車場を利用し、「丸屋」で医食同源の食事を提供し、
六合社の倉庫を「黒壁」に見たて、
「てしごとや」の委託販売された各店舗を見て歩き、市内を循環し、安楽寺で歴史に触れ、
長生社で地酒と地料理に舌鼓を打ち、まちの広場でイベントを楽しむ。
散歩を楽しみウォーキングを楽しむ。手仕事には「料理」も入ります。
地元の旬の食材を活用した様々な食堂や、青年海外協力隊の派遣先のエスニック料理店等が並ぶ町。
「手仕事屋のまち」として全国から人を呼び寄せます。
21世紀はクロスオーバーの時代です。多様性をくみ合わせ、
ネットワークする事で生き残りの道が開けてくるものと考えます。
(S.Ohara)

| 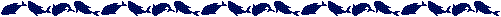

 PINE HILL
Mail:
ohara@komagane.com
PINE HILL
Mail:
ohara@komagane.com